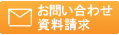収益認識基準と前受金管理の関係を解説
収益認識基準の基本
2021年度から全面適用された収益認識基準(企業会計基準第29号)は、「契約に基づく履行義務を充足した時点で収益を認識する」ことを原則としています。これにより、従来の「請求時点での収益計上」から、役務提供や商品引渡しに応じた収益認識へと変化しました。
前受金管理が必要となる理由
契約開始前やサービス提供前に代金を受け取った場合、その金額はまだ収益として認識できません。
- 商品やサービス提供前に受け取った代金は前受金(負債)として計上
- 実際に役務提供や商品引渡しが進んだ段階で、前受金から収益へ振替
この処理により、財務諸表は契約実態を正しく反映し、透明性が確保されます。
実務への影響
- 契約期間が複数月にわたる場合:月ごとの期間按分が必要
- 監査対応:前受金残高の正当性を説明する必要があり、明細管理が必須
- 内部統制:前受金と収益の対応関係が不明確だと、粉飾や誤謬のリスクにつながる
システム活用による解決
前受金管理を手作業で行うと、消込や期間按分の処理が煩雑になります。
専用システムを導入すれば、
- 契約情報に基づく自動期間按分
- 前受金残高の自動照合
- 監査用のエビデンス出力
が可能となり、効率化と制度遵守を両立できます。
サブスクに強い販売管理システムAllyなら
当社では、サブスクに強い販売管理システムAllyを開発・販売しています。Allyの導入をご検討される場合は、「サブスクの販売管理システムに特化しているコンサルはいるのか?」ということですが、そういったコンサルタントはなかなかいません。 そこで当社では、サブスク型ビジネスの業務フローや、販売管理システムについて特化したコンサルティングができるほどの知見を持つ営業担当者が、貴社のご相談に対応しています。 サブスク型ビジネスや定期請求が発生する業務をお持ちの企業様で、販売管理システムの導入をご検討の方は、当社までご相談ください。